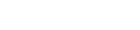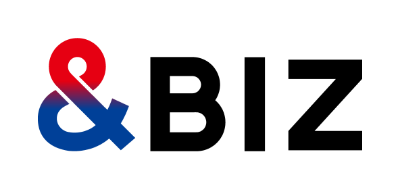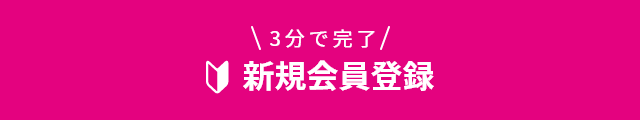2018.02.09
個性を束ねるチームマネージメントの流儀
会社は組織である以上、チームワークは普遍的に求められるテーマです。
考え方の異なるメンバーをまとめ、成果を上げなければならないリーダーは、時に壁に当たることもあるでしょう。
映画監督として多数の話題作を手掛けてきた行定勲さん。
制作現場はその道を究めてきたスタッフ、俳優陣など、ひと癖ある個性派揃いで、まとめ役である監督には、彼らを束ねるマネジメント力が必要となります。
スタッフや役者との向き合い方をはじめ、舵取りのテクニックなど、多彩な人材それぞれの能力を発揮できる環境づくりの秘訣をお話いただきました。
行定さんの持つ"束ねる力"が、マネジメントのヒントになるかもしれません。

監督と助監督は同じような仕事だと思われている人も多いと思いますが、実はまったく違うものです。
簡単にいうと、助監督は監督がイメージする現場の状況を創り上げて提示する役、監督は助監督が創ったものを肯定したり否定したりしながらイメージを確立していく役。
僕が助監督だった時代は、監督が提示しているイメージをどれだけ正確に具現化できるか、というところに面白みを感じていたんです。
でも監督になった今はそれができない。
助監督が用意した土台をベースに構築していくのが仕事なので、まずはスタッフに任せるしかないんです。
助手や撮影、照明、録音、美術、メイク、衣装、そして役者。
監督にとっては、専門分野を突き詰めた「プロ」である彼らが培ってきたイメージや才能が重要です。
そのためスタッフ選びは慎重になります。
場合によってはその才能が強すぎて、監督が翻弄されることもありますから。
自分が思い描いていたイメージをしっかり表現してくれる人選をしなければならないわけです。
例えば、ナーバスになりがちな俳優が主演の映画を撮るとしますよね。
そんな時は現場の雰囲気が非常に大切になるので、経験のある、かつ現場の空気を引っ張ってくれるような照明技師の方を起用したりします。
照明の光を含めて世界観を圧倒するというか、役者をその気にさせる力に期待して。
そうすると、みんなが監督である僕ではなく、その現場に集中するんですよね。
カメラマンとか照明さんとか、矢面に立ってつくっている人たちに。
僕はその裏で、監督として精査しなければならない作品の心理的な部分や映画の方向性などを考えることができます。
監督がセンターでスタンドプレイをしていると役者も監督に集中してしまって、自分で考えなくなるんですよね。
「監督はどうしたいですか、どうすればいいですか」と聞かれて答えを出しても、とうてい僕が言った通りにはなりませんから。
僕は、基本的に役者を放置したいんですよ。
役者がしっかりシナリオを読み込んで、用意された状況を把握して、自分自身の人生やアイデンティティみたいなものを重ね合わせて演技を考えてほしいんです。
監督もそうですが、人の上に立つ人間は、スタッフに考えさせる、思考させることが大切だと思っています。
そして、その間に自分も同じ立場に立って考える。
スタッフから10通りも20通りも案が出てきたとき、それをさらに越える「絶対にこれしかない」という1個のイメージを自分が出せるかどうか。
僕は映画の制作現場でもスタッフとこうした向き合い方をしています。
まずは答えを言わずに考えさせることが、よりよい結果に繋がるんですよね。

こう思うようになったのは、中学時代の出来事がきっかけです。
当時、バンドをやっていたこともあってすごいロン毛で。
頭髪検査の日、僕は校則どおり髪を三つ編みにしたんです。
「髪の長い生徒は三つ編みかおさげに」って書いてあったので(笑)。
もちろん呼び出されるわけですよ。
「男なのにその髪型はなんだ!」と先生からお叱りを受けて、「校則違反はしていない」と僕は屁理屈を並び立てました。
先生方との不毛な問答が続いた後、教頭先生が「わかった」と折れてくれたんです。
続けて「行定くん、ただね、社会に出たらもっと理不尽なルールがいっぱいあって、それを乗り越えていかないと思い通りの人生は歩めないんだよ。中学ではその訓練をしているだけだから、このくらいクリアできるだろ?」と。
その時、この人すごいな、と思って。
僕を受け入れてくれ、肯定した上で「君なりの人生を歩め」と教えてくれるなんて、懐の深い人だなと心に刺さりました。
どんな映画監督に言われた言葉より、教頭先生の言葉と行為が仕事をする上での基本になっていますね。
そして今も、こういう人でありたい、と思っています。
イラッとするものなんですよ。
どうでもいい意見と向き合って、一緒に遠回りをして、正しい道をお互いに見つけだそう、というスタイルですから。
企業でも僕らの仕事でも、時間がないのでなかなかできませんよね。
でも相手が真剣ならば、一回肯定して見直してみる価値はあると思います。
いい仕事をするためにも、いい作品をつくるためにも、その作業はムダにはなりませんから。
彼らが敏感にいろいろなものに反応して、思考することができているかを気にします。
彼らが楽しめること、生き生きとした仕事ぶりを遺憾なく発揮できることが、映画づくりでは大切なことなんです。
クリエイティブな発想を持ってもらうために僕がよくやるのは、決定権のない人間に決定権に近い質問を投げかけること。
例えば、「このシーンはアップと引き、どっちがいいと思う」と聞いてみるんです。
そう聞かれることで士気が上がるんですよね。
彼らはその場所に立って、一生懸命考えて「僕は引きがいいと思います」と答えを出す。
その答えを採用しなくても、真剣に考えた人間の言葉は「引っかかり」になって、いろんな意味で僕に力を与えてくれます。
権限がない部下を発想力がつくように育て、生き生きと仕事ができる環境をつくることも上に立つ者の役目ですよね。
人材を育てていく立場からすると、自分が上り詰めるのではなくて、自分を通過していった人間が上り詰めていく。
自分が嫉妬するような存在がどんどん生まれていくと、よりいい組織、いい現場になっていくんだろうな、と思います。

場所を変えるとその場の空気にも影響を受けます。
僕の場合、会議などで長い時間話し合うのは赤坂のオフィス、気心の知れた人間とラフに話をするのはアトリエと、仕事場を複数持つことで頭の中をリフレッシュしています。
アトリエで話したことや聞いたことが脚本のアイデアになることもよくあるんですよ。
さらに脚本の執筆など、自分個人で作業をするときはファミレスへ。
人がガチャガチャしている方が、不思議と集中力が増すんですよね。
企業で働く方も、一人で集中して何かを考えて創り上げたい時や、皆でブレストしたい時など、目的に応じて働く場所を変えてみるのもよいかもしれませんね。
「WORKSTYLING」のような快適で気持ちのいい場所で作業すれば、今までは考えつかなかった名案が浮かんできそうです。
行定監督のインタビュー Vol.2はこちら →
「個性を活かすチームマネジメント」
行定 勲
映画監督
ゆきさだ いさお/1968年、熊本県生まれ。
岩井俊二監督作品などで助監督を務め、2000年長編第1作の『ひまわり』(00)が第五回釜山国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。その後、『GO』(01)で日本アカデミー賞最優秀監督賞など数々の賞を受賞し、『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)は興行収入85億円の大ヒットを記録。その後の監督作に、『春の雪』(05)、『クローズド・ノート』(07)、『パレード』(10)、『ピンクとグレー』(16)、『ナラタージュ』(17)など。またドラマやCM、舞台演出など活動は多岐にわたる。
映画最新作は、2月公開の岡崎京子原作『リバーズ・エッジ』。
考え方の異なるメンバーをまとめ、成果を上げなければならないリーダーは、時に壁に当たることもあるでしょう。
映画監督として多数の話題作を手掛けてきた行定勲さん。
制作現場はその道を究めてきたスタッフ、俳優陣など、ひと癖ある個性派揃いで、まとめ役である監督には、彼らを束ねるマネジメント力が必要となります。
スタッフや役者との向き合い方をはじめ、舵取りのテクニックなど、多彩な人材それぞれの能力を発揮できる環境づくりの秘訣をお話いただきました。
行定さんの持つ"束ねる力"が、マネジメントのヒントになるかもしれません。

映画はスタッフの才能がすべて。彼らに任せるのが監督の仕事。
僕は監督になる前、助監督を約10年経験しています。監督と助監督は同じような仕事だと思われている人も多いと思いますが、実はまったく違うものです。
簡単にいうと、助監督は監督がイメージする現場の状況を創り上げて提示する役、監督は助監督が創ったものを肯定したり否定したりしながらイメージを確立していく役。
僕が助監督だった時代は、監督が提示しているイメージをどれだけ正確に具現化できるか、というところに面白みを感じていたんです。
でも監督になった今はそれができない。
助監督が用意した土台をベースに構築していくのが仕事なので、まずはスタッフに任せるしかないんです。
助手や撮影、照明、録音、美術、メイク、衣装、そして役者。
監督にとっては、専門分野を突き詰めた「プロ」である彼らが培ってきたイメージや才能が重要です。
そのためスタッフ選びは慎重になります。
場合によってはその才能が強すぎて、監督が翻弄されることもありますから。
自分が思い描いていたイメージをしっかり表現してくれる人選をしなければならないわけです。
監督に頼ってしまう現場からはいい作品は生まれない。
僕はスタッフを選ぶ基準は「人柄」や「相性」ですね。例えば、ナーバスになりがちな俳優が主演の映画を撮るとしますよね。
そんな時は現場の雰囲気が非常に大切になるので、経験のある、かつ現場の空気を引っ張ってくれるような照明技師の方を起用したりします。
照明の光を含めて世界観を圧倒するというか、役者をその気にさせる力に期待して。
そうすると、みんなが監督である僕ではなく、その現場に集中するんですよね。
カメラマンとか照明さんとか、矢面に立ってつくっている人たちに。
僕はその裏で、監督として精査しなければならない作品の心理的な部分や映画の方向性などを考えることができます。
監督がセンターでスタンドプレイをしていると役者も監督に集中してしまって、自分で考えなくなるんですよね。
「監督はどうしたいですか、どうすればいいですか」と聞かれて答えを出しても、とうてい僕が言った通りにはなりませんから。
僕は、基本的に役者を放置したいんですよ。
役者がしっかりシナリオを読み込んで、用意された状況を把握して、自分自身の人生やアイデンティティみたいなものを重ね合わせて演技を考えてほしいんです。
監督もそうですが、人の上に立つ人間は、スタッフに考えさせる、思考させることが大切だと思っています。
そして、その間に自分も同じ立場に立って考える。
スタッフから10通りも20通りも案が出てきたとき、それをさらに越える「絶対にこれしかない」という1個のイメージを自分が出せるかどうか。
僕は映画の制作現場でもスタッフとこうした向き合い方をしています。
まずは答えを言わずに考えさせることが、よりよい結果に繋がるんですよね。

イメージと異なっても一度肯定し、見直してみる価値はある。
僕はどんなに突拍子もない案をスタッフから提示されても、一度は肯定するように心がけています。こう思うようになったのは、中学時代の出来事がきっかけです。
当時、バンドをやっていたこともあってすごいロン毛で。
頭髪検査の日、僕は校則どおり髪を三つ編みにしたんです。
「髪の長い生徒は三つ編みかおさげに」って書いてあったので(笑)。
もちろん呼び出されるわけですよ。
「男なのにその髪型はなんだ!」と先生からお叱りを受けて、「校則違反はしていない」と僕は屁理屈を並び立てました。
先生方との不毛な問答が続いた後、教頭先生が「わかった」と折れてくれたんです。
続けて「行定くん、ただね、社会に出たらもっと理不尽なルールがいっぱいあって、それを乗り越えていかないと思い通りの人生は歩めないんだよ。中学ではその訓練をしているだけだから、このくらいクリアできるだろ?」と。
その時、この人すごいな、と思って。
僕を受け入れてくれ、肯定した上で「君なりの人生を歩め」と教えてくれるなんて、懐の深い人だなと心に刺さりました。
どんな映画監督に言われた言葉より、教頭先生の言葉と行為が仕事をする上での基本になっていますね。
そして今も、こういう人でありたい、と思っています。
イラッとするものなんですよ。
どうでもいい意見と向き合って、一緒に遠回りをして、正しい道をお互いに見つけだそう、というスタイルですから。
企業でも僕らの仕事でも、時間がないのでなかなかできませんよね。
でも相手が真剣ならば、一回肯定して見直してみる価値はあると思います。
いい仕事をするためにも、いい作品をつくるためにも、その作業はムダにはなりませんから。
気にかけているのは末端のスタッフ。彼らの発想力が自分の力になる。
監督という立場から気にするのは、決定権のない末端のスタッフのこと。彼らが敏感にいろいろなものに反応して、思考することができているかを気にします。
彼らが楽しめること、生き生きとした仕事ぶりを遺憾なく発揮できることが、映画づくりでは大切なことなんです。
クリエイティブな発想を持ってもらうために僕がよくやるのは、決定権のない人間に決定権に近い質問を投げかけること。
例えば、「このシーンはアップと引き、どっちがいいと思う」と聞いてみるんです。
そう聞かれることで士気が上がるんですよね。
彼らはその場所に立って、一生懸命考えて「僕は引きがいいと思います」と答えを出す。
その答えを採用しなくても、真剣に考えた人間の言葉は「引っかかり」になって、いろんな意味で僕に力を与えてくれます。
権限がない部下を発想力がつくように育て、生き生きと仕事ができる環境をつくることも上に立つ者の役目ですよね。
人材を育てていく立場からすると、自分が上り詰めるのではなくて、自分を通過していった人間が上り詰めていく。
自分が嫉妬するような存在がどんどん生まれていくと、よりいい組織、いい現場になっていくんだろうな、と思います。

ファミレスで集中力がアップ!場所を変えれば発想も変わる。
上司や取引先も乗り気になるような新たな発想を生み出すには、考える場所も大切です。場所を変えるとその場の空気にも影響を受けます。
僕の場合、会議などで長い時間話し合うのは赤坂のオフィス、気心の知れた人間とラフに話をするのはアトリエと、仕事場を複数持つことで頭の中をリフレッシュしています。
アトリエで話したことや聞いたことが脚本のアイデアになることもよくあるんですよ。
さらに脚本の執筆など、自分個人で作業をするときはファミレスへ。
人がガチャガチャしている方が、不思議と集中力が増すんですよね。
企業で働く方も、一人で集中して何かを考えて創り上げたい時や、皆でブレストしたい時など、目的に応じて働く場所を変えてみるのもよいかもしれませんね。
「WORKSTYLING」のような快適で気持ちのいい場所で作業すれば、今までは考えつかなかった名案が浮かんできそうです。
行定監督のインタビュー Vol.2はこちら →
COMMONS PAGEメンバー限定
行定 勲さんの講演会を開催!
今回のテーマは、行定 勲さんの講演会を開催!
「個性を活かすチームマネジメント」
〜現場の発想力を力に〜
講演日時:2018年4月11日(水) 18:30開演 20:00終了予定
場所:東京ミッドタウン・カンファレンス Room9
人数:COMMONS PAGEメンバー限定80名様をご招待
応募は締め切りました。
場所:東京ミッドタウン・カンファレンス Room9
人数:COMMONS PAGEメンバー限定80名様をご招待
応募は締め切りました。
行定 勲
映画監督
ゆきさだ いさお/1968年、熊本県生まれ。
岩井俊二監督作品などで助監督を務め、2000年長編第1作の『ひまわり』(00)が第五回釜山国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。その後、『GO』(01)で日本アカデミー賞最優秀監督賞など数々の賞を受賞し、『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)は興行収入85億円の大ヒットを記録。その後の監督作に、『春の雪』(05)、『クローズド・ノート』(07)、『パレード』(10)、『ピンクとグレー』(16)、『ナラタージュ』(17)など。またドラマやCM、舞台演出など活動は多岐にわたる。
映画最新作は、2月公開の岡崎京子原作『リバーズ・エッジ』。
※本サイトのサービス名称は、2023年3月31日より「&BIZ」へ名称変更いたしました。
-
2023.11.10
NECネッツエスアイ提供セミナー「乳がんとの向き合い方~家族や職場の理解と共感~」開催レポート
-
2023.11.01
3,000社の知の頂点はどの企業に!?クイズ大会決勝進出チーム決定!
-
2023.10.24
数百人の会社員が熱唱する、「新宿のど自慢大会」の舞台裏
-
2023.10.24
カラダと向き合う「Health Forum」~みんなで学ぼう女性の健康~開催レポート
-
2023.10.20
多様な社員が活躍し、つながり合える本社オフィスを実現
-
2023.10.06
三井不動産の「課題解決」はなぜ、ここまでやるのか
-
2023.10.02
「介護セミナーゼロから始める介護のはなし~介護で仕事を辞めないために~」開催レポート
-
2023.09.11
第5回『三井のオフィス』会社対抗横断クイズ 2023参加者募集開始!


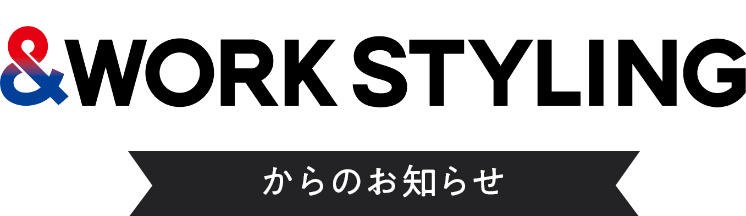
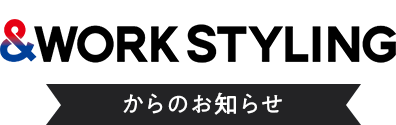

 は
は