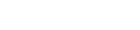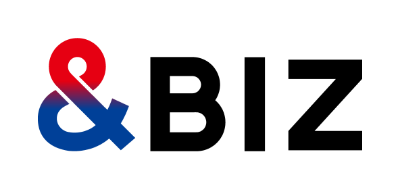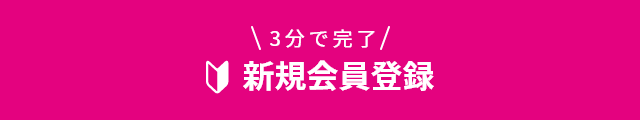2018.03.30
型にはまらないのが映画人たちを束ねるマネジメント術
話題の映画を数多く手掛けている行定勲監督に、個性派集団を束ねるチームマネジメント術について話をお聞きするインタビューの第二弾。
困難を乗り越えるためにすべきことや、独自のシナリオのつくり方など、仕事でつまずいた時や大切な資料づくりの役に立ちそうな話をお伺いしました。

そんな時は、一番メンタルに強い俳優を滅多打ちにすることがあります。
別にその人が悪いわけじゃないんです。
でも経験が浅くてメンタルの弱い俳優を叩いてしまうと、何もできなくなってしまうじゃないですか。
だからメンタルが強い俳優に白羽の矢を立てて、「もう1回、もう1回」と追い込んでいくんです。
すると全体がだんだん良くなっていくし、経験の浅い役者たちは有利になるんですよ。
できる先輩が叩かれることで、自分たちは「がんばりましょうよ!」と言える立場になるので。
それでも、撮影終わりには僕がぼろくそに言うので、みんな落ち込むわけです。
そこで「照明もカメラマンもスタッフみんなが君たちのことを素晴らしいと言っているよ。僕以外はね」というと、彼らはその言葉に支えられるものなんです。
要はチーム全体の士気が落ちないようにすることが大切。
打ってもへこたれないところを叩くことで全体が引き締まり、認めてくれる人がいることが力になる。
思い通りにならないからと頭ごなしに弱い人間を叩いても何も良いことはありません。
上に立つ者は常に全体を俯瞰で見ながら、どうすればより良い方向に舵を取れるのかを熟慮しなければなりません。

自分のイメージに引き寄せることもありますし、こっちが彼らのイメージに近づけることもあります。
基本的に役者は、「自分がこの役をどう生きるか」ということを真剣に考えて向き合った上で、その場面を演じているわけですから。
そこに対する擦り合わせは必要だと思っています。
演技に正解はないですからね。
例えば台本には「泣く」と書いてあっても、笑ってもいいわけですよ。
笑っていても泣いている以上に悲しみが伝わることもあるので。
「泣く」と書いてあるところで泣くのは簡単ですが、笑っているけど心では泣いてるんだな、というのがわかると、こっちも泣かされます。
俳優の中に「役を生きる覚悟」がある程度見えれば、台本のあるドキュメンタリーみたいなもの。
どのシーンで何をしゃべってもカタチになるものです。
基本的には規律やルールは破っていい、という前提の元にあると僕は思っていますから。
ある程度のルールを設定するのは最低限の秩序を保つため。
でも「右に行っちゃダメ」というルールがあるところで「右からの方が近いから行っちゃえ」というのが映画なんです。
それで事故が起こるかもしれませんが、それが映画。
人の道をちょっとだけ外れるけれど、みんながそういう気持ちを持っていなければ面白い作品はつくれません。
もしかしたら、企業でもそういう部分が少しあった方が型にはまらない妙案が出てくるのかもしれませんね。

「前例がない」というだけで道が塞がれてしまうこともよくあること。
その場合は諦めずに考え方を変えて、浮かんだ案を実行することが大切です。
僕も壁を越えるためにいろんな抜け道を見つけてきました。
10年以上あたため続けていて成立しなかった作品が、人気俳優の「やりたい」のひと言で映画化されたり、日本では見向きもされなかった作品が海外に持って行ったことで話題になって現地企業の協力が得られたり。
タイミングや場所によっても状況は変わります。
だから壁にぶち当たった時は無理によじ登ろうとしないことです。
ちょっと遠回りすると意外なところに隙間があったりするので、そこから突破すればいいんです。
場合によっては苦手な人が壁になることもありますよね。
仕事を続けていくと、絶対と言っていいほど自分と合わない相手が出てきますから。
正直、僕も「センスがなくてどうしようもないな」という人に出会った経験があります。
そういう場合は潔く諦めますね。
一度諦めると自分の中の基準が変わるんですよ。
道が開けるというよりは、諦めたなりの良さがある、という感じ。
自分が想像もしなかった気持ちになることもあるので、人に対しては「諦めが肝心」なのかもしれません。
さらに言うなら、理想もあまり高く持ちすぎない方がいいと思っています。
理想が高いと考え方がガチガチになってしまって、自由な発想が生まれないような気がして。
仕事をする上では「高い理想」ではなく「ひとつの強い信念」を持つこと、そしてフレキシブルに動くことが思いを実現させるポイントだと思います。

自分の思い出話を人に話すことで形になったり、スタッフや仕事仲間との会話の中からアイデアが浮かんだり。
常に疑問に思っていることや「こういう人がいたんだよね」といった話から発想が膨らんでいくこともあります。
作業的には落語や小話をつくる感覚に似ているかもしれません。
面白い話をみんなに聞かせてオチをつくるところとか、人に話していくたびにブラッシュアップされていくところとか。
だから、思っていることを誰かに話すことはすごく大事だと思うんです。
話すたびにエピソードは面白くなって、強くなっていくんですよね。
エピソードが強靱でないと映画になった時に弱くなってしまって心に残りませんから。
僕が何かをつくる場合、まずは早いうちにスタンダードなものをつくり上げてしまうのが基本です。
それをいろんな場所に持ち込んで書き換えていく。
環境が変わると発想も変わるのでどんどんブラッシュアップしていくと、最終的には全然違うものになるんですよね。
だからシナリオをつくる時は、へぼいセリフでもいいから最後までストーリーが繋がるものを一気に書き上げます。
作業に集中できるファミレスでね(笑)。
それを長い時間かけて、場所を変えてはブラッシュアップしていく。
そうするとストーリーも変わっていってより洗練された作品になっていくんです。
みなさんも企画書など大切な資料をつくる時は、この方法で仕上げるとより良いものがつくれるかもしれませんよ。
行定監督のインタビュー Vol.1はこちら →
行定 勲
映画監督
ゆきさだ いさお/1968年、熊本県生まれ。
岩井俊二監督作品などで助監督を務め、2000年長編第1作の『ひまわり』(00)が第五回釜山国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。その後、『GO』(01)で日本アカデミー賞最優秀監督賞など数々の賞を受賞し、『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)は興行収入85億円の大ヒットを記録。その後の監督作に、『春の雪』(05)、『クローズド・ノート』(07)、『パレード』(10)、『ピンクとグレー』(16)、『ナラタージュ』(17)など。またドラマやCM、舞台演出など活動は多岐にわたる。
映画最新作は、2月公開の岡崎京子原作『リバーズ・エッジ』。
困難を乗り越えるためにすべきことや、独自のシナリオのつくり方など、仕事でつまずいた時や大切な資料づくりの役に立ちそうな話をお伺いしました。

場の空気を引き締めるためには全体を俯瞰で見ることが大切。
例えば、俳優陣の場の雰囲気を引き締めたい時があるとしますよね。そんな時は、一番メンタルに強い俳優を滅多打ちにすることがあります。
別にその人が悪いわけじゃないんです。
でも経験が浅くてメンタルの弱い俳優を叩いてしまうと、何もできなくなってしまうじゃないですか。
だからメンタルが強い俳優に白羽の矢を立てて、「もう1回、もう1回」と追い込んでいくんです。
すると全体がだんだん良くなっていくし、経験の浅い役者たちは有利になるんですよ。
できる先輩が叩かれることで、自分たちは「がんばりましょうよ!」と言える立場になるので。
それでも、撮影終わりには僕がぼろくそに言うので、みんな落ち込むわけです。
そこで「照明もカメラマンもスタッフみんなが君たちのことを素晴らしいと言っているよ。僕以外はね」というと、彼らはその言葉に支えられるものなんです。
要はチーム全体の士気が落ちないようにすることが大切。
打ってもへこたれないところを叩くことで全体が引き締まり、認めてくれる人がいることが力になる。
思い通りにならないからと頭ごなしに弱い人間を叩いても何も良いことはありません。
上に立つ者は常に全体を俯瞰で見ながら、どうすればより良い方向に舵を取れるのかを熟慮しなければなりません。

映画づくりにはルールを破るような型にはまらない精神が不可欠。
自分のイメージと役者の演技に差が生じた時は、彼らのアプローチに対してどう向き合うかを考えますね。自分のイメージに引き寄せることもありますし、こっちが彼らのイメージに近づけることもあります。
基本的に役者は、「自分がこの役をどう生きるか」ということを真剣に考えて向き合った上で、その場面を演じているわけですから。
そこに対する擦り合わせは必要だと思っています。
演技に正解はないですからね。
例えば台本には「泣く」と書いてあっても、笑ってもいいわけですよ。
笑っていても泣いている以上に悲しみが伝わることもあるので。
「泣く」と書いてあるところで泣くのは簡単ですが、笑っているけど心では泣いてるんだな、というのがわかると、こっちも泣かされます。
俳優の中に「役を生きる覚悟」がある程度見えれば、台本のあるドキュメンタリーみたいなもの。
どのシーンで何をしゃべってもカタチになるものです。
基本的には規律やルールは破っていい、という前提の元にあると僕は思っていますから。
ある程度のルールを設定するのは最低限の秩序を保つため。
でも「右に行っちゃダメ」というルールがあるところで「右からの方が近いから行っちゃえ」というのが映画なんです。
それで事故が起こるかもしれませんが、それが映画。
人の道をちょっとだけ外れるけれど、みんながそういう気持ちを持っていなければ面白い作品はつくれません。
もしかしたら、企業でもそういう部分が少しあった方が型にはまらない妙案が出てくるのかもしれませんね。

よじ登るのは得策ではない。大きな壁を突破する秘訣とは?
新しいものを生み出すことは、映画制作だけでなく企業でも大変なことですよね。「前例がない」というだけで道が塞がれてしまうこともよくあること。
その場合は諦めずに考え方を変えて、浮かんだ案を実行することが大切です。
僕も壁を越えるためにいろんな抜け道を見つけてきました。
10年以上あたため続けていて成立しなかった作品が、人気俳優の「やりたい」のひと言で映画化されたり、日本では見向きもされなかった作品が海外に持って行ったことで話題になって現地企業の協力が得られたり。
タイミングや場所によっても状況は変わります。
だから壁にぶち当たった時は無理によじ登ろうとしないことです。
ちょっと遠回りすると意外なところに隙間があったりするので、そこから突破すればいいんです。
場合によっては苦手な人が壁になることもありますよね。
仕事を続けていくと、絶対と言っていいほど自分と合わない相手が出てきますから。
正直、僕も「センスがなくてどうしようもないな」という人に出会った経験があります。
そういう場合は潔く諦めますね。
一度諦めると自分の中の基準が変わるんですよ。
道が開けるというよりは、諦めたなりの良さがある、という感じ。
自分が想像もしなかった気持ちになることもあるので、人に対しては「諦めが肝心」なのかもしれません。
さらに言うなら、理想もあまり高く持ちすぎない方がいいと思っています。
理想が高いと考え方がガチガチになってしまって、自由な発想が生まれないような気がして。
仕事をする上では「高い理想」ではなく「ひとつの強い信念」を持つこと、そしてフレキシブルに動くことが思いを実現させるポイントだと思います。

場所を変えてブラッシュアップ。その繰り返しが脚本づくりの基本。
僕は脚本も手掛けていますが、発想が思い浮かぶのはふとした瞬間です。自分の思い出話を人に話すことで形になったり、スタッフや仕事仲間との会話の中からアイデアが浮かんだり。
常に疑問に思っていることや「こういう人がいたんだよね」といった話から発想が膨らんでいくこともあります。
作業的には落語や小話をつくる感覚に似ているかもしれません。
面白い話をみんなに聞かせてオチをつくるところとか、人に話していくたびにブラッシュアップされていくところとか。
だから、思っていることを誰かに話すことはすごく大事だと思うんです。
話すたびにエピソードは面白くなって、強くなっていくんですよね。
エピソードが強靱でないと映画になった時に弱くなってしまって心に残りませんから。
僕が何かをつくる場合、まずは早いうちにスタンダードなものをつくり上げてしまうのが基本です。
それをいろんな場所に持ち込んで書き換えていく。
環境が変わると発想も変わるのでどんどんブラッシュアップしていくと、最終的には全然違うものになるんですよね。
だからシナリオをつくる時は、へぼいセリフでもいいから最後までストーリーが繋がるものを一気に書き上げます。
作業に集中できるファミレスでね(笑)。
それを長い時間かけて、場所を変えてはブラッシュアップしていく。
そうするとストーリーも変わっていってより洗練された作品になっていくんです。
みなさんも企画書など大切な資料をつくる時は、この方法で仕上げるとより良いものがつくれるかもしれませんよ。
行定監督のインタビュー Vol.1はこちら →
行定 勲
映画監督
ゆきさだ いさお/1968年、熊本県生まれ。
岩井俊二監督作品などで助監督を務め、2000年長編第1作の『ひまわり』(00)が第五回釜山国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。その後、『GO』(01)で日本アカデミー賞最優秀監督賞など数々の賞を受賞し、『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)は興行収入85億円の大ヒットを記録。その後の監督作に、『春の雪』(05)、『クローズド・ノート』(07)、『パレード』(10)、『ピンクとグレー』(16)、『ナラタージュ』(17)など。またドラマやCM、舞台演出など活動は多岐にわたる。
映画最新作は、2月公開の岡崎京子原作『リバーズ・エッジ』。
-
2023.03.15
社内コミュニケーションを深め、生産性・快適性を高めるオフィスレイアウト改革
-
2023.03.09
『三井のオフィス』 各種ソフトサービスのサービス名称及びロゴを刷新。
スローガンも新たに、「COLORFUL WORK(カラフルワーク)」と制定。 -
2023.02.27
東京・春・音楽祭 ――春の上野は音楽も満開
-
2023.02.21
組織を超えたつながりを深め、コラボレーションを促進する「共創」のための新オフィス
-
2023.02.20
&well健康コラム|マスクが誘発!? 口周りのトラブル
-
2023.02.20
「介護セミナー 認知症入門
~支える人に知っておいて欲しいこと~」開催レポート -
2023.02.06
【くらしのコラム】無意識に働きかける木の不思議な効果
-
2023.01.23
&well健康コラム|
朝食を制する者は、健康を制する


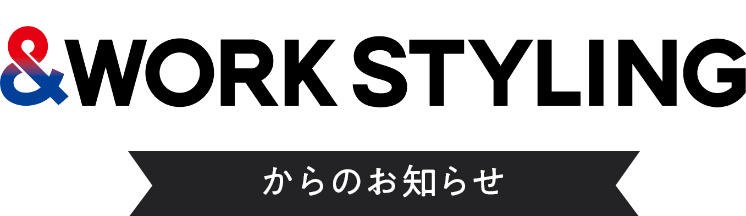
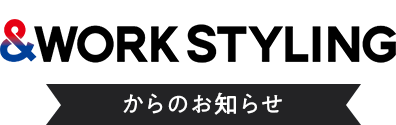

 は
は