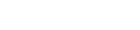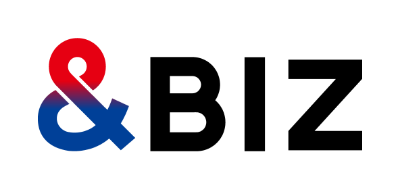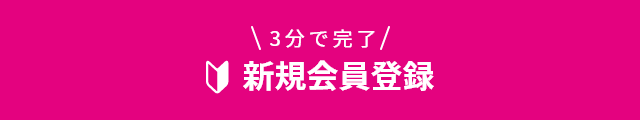2018.06.13
行定勲さんのトークセッションレポート! 「個性を活かすチームマネジメント」~現場の発想力を力に~
『三井のオフィス』で働くビジネスパーソンの気づきやヒントになり、仕事やオフタイムの充実を図っていただきたいという想いで開催される、COMMONS PAGEメンバー限定の特別イベント。
4月11日(水)に開催されたのは、映画監督としてさまざまな話題作を世に送り出している行定勲さんの講演会です。
映画監督といえば、個性的なスタッフを束ねなければならないため、チームマネジメントの力が必要です。今回は、スタッフの能力を引き出す方法や、スタッフをまとめ上げるための秘策など、その極意を教えていただきます。
行定さんからどのようなお話が聞けたのか、会場の雰囲気とともにお届けします。
まずお話いただいたのは映画監督を目指したきっかけについて。
小学生の頃、黒澤明監督作品『影武者』の撮影現場を見て、映画監督ではなく「映画をつくる人になりたい」と思ったという行定監督。
完成した『影武者』を観に行った時、リアルな戦国時代が再現されていて驚いたこと、作品本編ではなくエンドロールを見るために2度も観に行ったこと、スタッフの人数を数えてみたら200人くらいいて、その中の1人にはなれるのではないかと思ったことなど、当時の記憶をよみがえらせます。

講演会では、監督の仕事ぶりを記録した映画のメイキング映像も公開されました。
熊本県出身の行定監督が、初めて故郷を舞台に撮影した中編映画『うつくしいひと』の続編である『うつくしいひと サバ?』のメイキングです。
2016年に公開された『うつくしいひと』を撮影したのは熊本地震が起こる前。そして『うつくしいひと サバ?』は地震の震源地で甚大な被害を受けた益城町を舞台に選んだそう。
「こんな状況で撮影するのか」と反対する地域住民もいたため、制作サイドには葛藤があったことや、そこをどう乗り越えたのかを詳しくお話いただきました。
本震の際は監督自身も熊本にいたそうで、故郷に対するさまざまな思いが溢れ出します。
「やがてこの場所は復興を遂げて新しい町に変わり、震災時の記憶や感情が風化してしまいます。だから崩壊した熊本の風景や地域の人々の感情を物語として残しておかないと、と思ったんです。記録は記憶に有効ですし、映画は文化として残るもの。そのためにも映画にしたかったんです」
そう熱く語る行定監督がとても印象的でした。
「映画監督にはいろいろなやり方がありますが、僕の場合はあまりずる賢い処世術を使わず、自分が思っていることを包み隠さずスタッフにぶつけることにしています。
当然、批判はあります。現場のスタッフは職人の集まりですから、自分の思いや表現法があるわけです。"監督はそういったけど、こういうのはどう?"という提案に対しては必ず耳を貸します。それがいい結果に繋がることもたくさんありますから。
ある作品で、拳銃を撃つシーンがあったんですよ。その場合、音の職人が拳銃の音をつくるわけです。最初は100人くらい殺せるような大きな音を出していたので、"ちょっと音が大きすぎるような気がするんだけど"と伝えました。何度やっても、抑えてはいるもののデカすぎる。そして本番。最後に出た音は、彼が音のプロとしてたくさんの音をつくってきた経験から、これ以下にしたらダメな音だったんでしょう。実はその時も僕はまだ音が大きすぎると思っていましたが、この音を採用することにしました。
でも1年後くらいに観てみると、このくらい大きい音の方が心に刺さるんだ、印象に残るんだ、ということわかるんです。映画の現場にはそんなことがたくさんあります。

まずはその人を認めて、自分の引きどころをつくることが大切です。完璧を求めるなら監督の権限を振りかざして言う通りにやってもらえばいいだけですが、それをやり始めたら"俺じゃなくていいだろう"となってしまう。映画のスタッフはみんなそう。役者もそう。だからこそ、チームの長として彼らの意見に耳を傾けること、そして場合によっては彼らの意見を尊重することが必要なんです」
これは会社内でチームマネジメントをする立場の人にも通じるものがあります。円滑に仕事を回すためにも部下を信じて、彼らの言うことにも耳を傾けることが必要なのかもしれませんね。
「スタッフはみんなその道のプロですから、譲れないプライドがある。ガチンコでぶつかってくるので、それを束ねるのはほぼ無理なんです(笑)。だからそのプライドを逆手にとって、やる気にさせることもよくあります。
無理難題を脚本の中に組み込んだりするんですよ。照明スタッフへの指示で"ここで奇跡的な光が降り注ぐ"みたいな。そうすると"奇跡的な光ってどんな光だろう"って考えるんですよね。そこに気を取られているから、他の事はだいたい指示通りにやってくれます(笑)。自分の見せ場がここにあるんだ、ということが明確にわかっていますから。無理強いすると、いい結果にならないものです。
正直なところ、僕は自分が作った映画なんてたいしたことないと思っているんですよ。でも10年振りに観たりすると感動するんですよね。作品に参加した人たちの思いがちゃんと残っている感じがして、自分の思い通りにならなくても"これでよかったんだと"と思える。目標からはズレていても、いい到達点だったと実感するんです」
予定調和ではおもしろくない、ちょっとズレている方がいい作品ができる、というのが行定監督の持論です。そのちょっとしたズレを生み出しているのが職人気質の現場スタッフ。
会社でもチームスタッフのプライドを上手にコントロールしてヤル気にさせることが、いい結果を生み出す秘訣のようです。
笑いを交えて楽しく興味深いお話をたくさん語っていただき、トークセッションは予定の時間をオーバー。あまりに映画の話が弾んでしまったため「こんな感じで大丈夫ですか? 台本が全然進んでないけど(笑)」と監督が心配するシーンも。
講演会でも予定調和におさめないところが、いかにも行定監督らしいですね。
「今日は3時間やりますから。みなさん、適当に帰っていいですからね」と最後に来場者の笑いを誘うところは、さすがのひと言です。

休憩を挟んだ後は、質疑応答の時間です。「何を聞いてもオッケー」という監督に、来場者からさまざまな質問が投げかけられました。
モチベーションが低いスタッフを上手に動かす方法など、ビジネスシーンでアドバイスを求める方に、丁寧に行定流の答えを導き出します。来場者のみなさんもビジネスのヒントを拾い集めようと熱心に耳を傾けていました。

すべてが終了し、大きな拍手で見送られる行定監督。
その熱のこもった拍手は満足度が高かった証拠。来場者のみなさんも百戦錬磨でチームマネジメント力に長けた監督の話に刺激をもらって、会場を後にしたようです。
4月11日(水)に開催されたのは、映画監督としてさまざまな話題作を世に送り出している行定勲さんの講演会です。
映画監督といえば、個性的なスタッフを束ねなければならないため、チームマネジメントの力が必要です。今回は、スタッフの能力を引き出す方法や、スタッフをまとめ上げるための秘策など、その極意を教えていただきます。
行定さんからどのようなお話が聞けたのか、会場の雰囲気とともにお届けします。
メイキング映像をきっかけに語られた故郷への思い。
会場を埋めつくした来場者の大きな拍手で迎えられた行定勲監督。今回のトークセッションはインタビュアーの質問に行定監督が答えていくという形で進められます。まずお話いただいたのは映画監督を目指したきっかけについて。
小学生の頃、黒澤明監督作品『影武者』の撮影現場を見て、映画監督ではなく「映画をつくる人になりたい」と思ったという行定監督。
完成した『影武者』を観に行った時、リアルな戦国時代が再現されていて驚いたこと、作品本編ではなくエンドロールを見るために2度も観に行ったこと、スタッフの人数を数えてみたら200人くらいいて、その中の1人にはなれるのではないかと思ったことなど、当時の記憶をよみがえらせます。

講演会では、監督の仕事ぶりを記録した映画のメイキング映像も公開されました。
熊本県出身の行定監督が、初めて故郷を舞台に撮影した中編映画『うつくしいひと』の続編である『うつくしいひと サバ?』のメイキングです。
2016年に公開された『うつくしいひと』を撮影したのは熊本地震が起こる前。そして『うつくしいひと サバ?』は地震の震源地で甚大な被害を受けた益城町を舞台に選んだそう。
「こんな状況で撮影するのか」と反対する地域住民もいたため、制作サイドには葛藤があったことや、そこをどう乗り越えたのかを詳しくお話いただきました。
本震の際は監督自身も熊本にいたそうで、故郷に対するさまざまな思いが溢れ出します。
「やがてこの場所は復興を遂げて新しい町に変わり、震災時の記憶や感情が風化してしまいます。だから崩壊した熊本の風景や地域の人々の感情を物語として残しておかないと、と思ったんです。記録は記憶に有効ですし、映画は文化として残るもの。そのためにも映画にしたかったんです」
そう熱く語る行定監督がとても印象的でした。
明確に自分の意思をぶつけ、スタッフの意見にも耳を傾ける。
続いて、映画監督として大勢のスタッフを束ねる秘訣についても語られました。「映画監督にはいろいろなやり方がありますが、僕の場合はあまりずる賢い処世術を使わず、自分が思っていることを包み隠さずスタッフにぶつけることにしています。
当然、批判はあります。現場のスタッフは職人の集まりですから、自分の思いや表現法があるわけです。"監督はそういったけど、こういうのはどう?"という提案に対しては必ず耳を貸します。それがいい結果に繋がることもたくさんありますから。
ある作品で、拳銃を撃つシーンがあったんですよ。その場合、音の職人が拳銃の音をつくるわけです。最初は100人くらい殺せるような大きな音を出していたので、"ちょっと音が大きすぎるような気がするんだけど"と伝えました。何度やっても、抑えてはいるもののデカすぎる。そして本番。最後に出た音は、彼が音のプロとしてたくさんの音をつくってきた経験から、これ以下にしたらダメな音だったんでしょう。実はその時も僕はまだ音が大きすぎると思っていましたが、この音を採用することにしました。
でも1年後くらいに観てみると、このくらい大きい音の方が心に刺さるんだ、印象に残るんだ、ということわかるんです。映画の現場にはそんなことがたくさんあります。

まずはその人を認めて、自分の引きどころをつくることが大切です。完璧を求めるなら監督の権限を振りかざして言う通りにやってもらえばいいだけですが、それをやり始めたら"俺じゃなくていいだろう"となってしまう。映画のスタッフはみんなそう。役者もそう。だからこそ、チームの長として彼らの意見に耳を傾けること、そして場合によっては彼らの意見を尊重することが必要なんです」
これは会社内でチームマネジメントをする立場の人にも通じるものがあります。円滑に仕事を回すためにも部下を信じて、彼らの言うことにも耳を傾けることが必要なのかもしれませんね。
プライドを刺激して無理難題を与えることで舵取りをスムーズに。
すべてが自分の思い通りになることは、まずないという行定監督。そんなひと癖もふた癖もあるスタッフを束ね、自分が思い描いている形に近づけるためにはどのような技を使っているのでしょうか?「スタッフはみんなその道のプロですから、譲れないプライドがある。ガチンコでぶつかってくるので、それを束ねるのはほぼ無理なんです(笑)。だからそのプライドを逆手にとって、やる気にさせることもよくあります。
無理難題を脚本の中に組み込んだりするんですよ。照明スタッフへの指示で"ここで奇跡的な光が降り注ぐ"みたいな。そうすると"奇跡的な光ってどんな光だろう"って考えるんですよね。そこに気を取られているから、他の事はだいたい指示通りにやってくれます(笑)。自分の見せ場がここにあるんだ、ということが明確にわかっていますから。無理強いすると、いい結果にならないものです。
正直なところ、僕は自分が作った映画なんてたいしたことないと思っているんですよ。でも10年振りに観たりすると感動するんですよね。作品に参加した人たちの思いがちゃんと残っている感じがして、自分の思い通りにならなくても"これでよかったんだと"と思える。目標からはズレていても、いい到達点だったと実感するんです」
予定調和ではおもしろくない、ちょっとズレている方がいい作品ができる、というのが行定監督の持論です。そのちょっとしたズレを生み出しているのが職人気質の現場スタッフ。
会社でもチームスタッフのプライドを上手にコントロールしてヤル気にさせることが、いい結果を生み出す秘訣のようです。
講演会も予定調和で終わらせないのが行定監督の流儀。
このほか、監督の代表作と言われ、85億円もの興行収入を叩き出した『世界の中心で、愛をさけぶ』の作品に込めた思いや制作秘話など、業界の裏話まで暴露してくれた行定監督。笑いを交えて楽しく興味深いお話をたくさん語っていただき、トークセッションは予定の時間をオーバー。あまりに映画の話が弾んでしまったため「こんな感じで大丈夫ですか? 台本が全然進んでないけど(笑)」と監督が心配するシーンも。
講演会でも予定調和におさめないところが、いかにも行定監督らしいですね。
「今日は3時間やりますから。みなさん、適当に帰っていいですからね」と最後に来場者の笑いを誘うところは、さすがのひと言です。

休憩を挟んだ後は、質疑応答の時間です。「何を聞いてもオッケー」という監督に、来場者からさまざまな質問が投げかけられました。
モチベーションが低いスタッフを上手に動かす方法など、ビジネスシーンでアドバイスを求める方に、丁寧に行定流の答えを導き出します。来場者のみなさんもビジネスのヒントを拾い集めようと熱心に耳を傾けていました。

すべてが終了し、大きな拍手で見送られる行定監督。
その熱のこもった拍手は満足度が高かった証拠。来場者のみなさんも百戦錬磨でチームマネジメント力に長けた監督の話に刺激をもらって、会場を後にしたようです。
※本サイトのサービス名称は、2023年3月31日より「&BIZ」へ名称変更いたしました。
-
2023.11.10
NECネッツエスアイ提供セミナー「乳がんとの向き合い方~家族や職場の理解と共感~」開催レポート
-
2023.11.01
3,000社の知の頂点はどの企業に!?クイズ大会決勝進出チーム決定!
-
2023.10.24
数百人の会社員が熱唱する、「新宿のど自慢大会」の舞台裏
-
2023.10.24
カラダと向き合う「Health Forum」~みんなで学ぼう女性の健康~開催レポート
-
2023.10.20
多様な社員が活躍し、つながり合える本社オフィスを実現
-
2023.10.06
三井不動産の「課題解決」はなぜ、ここまでやるのか
-
2023.10.02
「介護セミナーゼロから始める介護のはなし~介護で仕事を辞めないために~」開催レポート
-
2023.09.11
第5回『三井のオフィス』会社対抗横断クイズ 2023参加者募集開始!


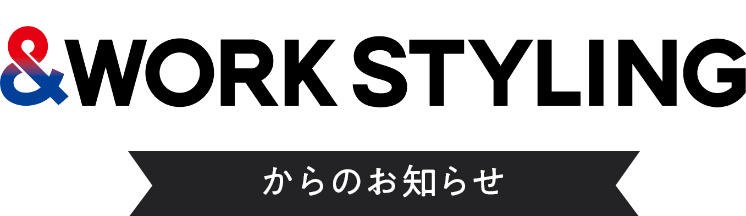
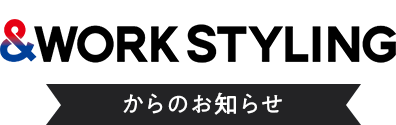

 は
は